飲食店のリピート率を上げて成功するお店の共通点とは?

「昔からのお客様が最近減ってきた気がする…」そんな飲食店に向けて、リピート率を改善するための施策や考え方を分かりやすく解説します。この記事では、個人経営の老舗飲食店が実践しやすい、コストを抑えた工夫・接客のポイント・顧客との関係づくりなどを具体例を交えて紹介します。派手な広告に頼らず、地元のお客様に「また来たい」と思ってもらえるお店を目指しましょう。
目次
- 飲食店のリピート率とは?
- 飲食店の平均的なリピート率
- リピーター育成の鍵は継続的な接点づくり~toypoの活用~
- リピーターが多い飲食店の特徴
- リピーターを増やすと飲食店が得られるメリット
- リピーターが増えない飲食店の問題点
- リピーターを増やすための具体的な施策
- まとめ:地道な販促とデジタル活用で安定経営を目指そう
飲食店のリピート率とは?

リピート率とは、一度お店を利用したお客様が、もう一度来店してくれる割合のことを指します。新規集客ばかりに注力するのではなく、来てくれたお客様に「また行きたい」と思ってもらえる仕組みを作ることが、飲食店経営の安定には不可欠です。
この指標は、お店の満足度や信頼性のバロメーターとも言えます。料理の味、接客、雰囲気、立地など、さまざまな要素が影響するため、単なる数値ではなく、総合的な店づくりの成果が現れるものです。
飲食店においては「リピーターがいる=お店のファンがいる」ということ。リピート率を高めることは、売上の安定化・販促コストの削減・口コミによる新規獲得にもつながる、非常に重要な経営指標です。
リピート率の定義と計算方法
リピート率とは、新規で来店したお客様のうち、一定期間内に再来店してくれた人の割合を指します。飲食店の経営においては、「新規をどう呼ぶか」だけでなく、「来てくれた人をいかにリピーターに育てるか」が重要な視点になります。
■ リピート率の計算式
リピート率(%) = リピーター数 ÷ 新規来店者数 × 100
たとえば、ある月に100人の新規来店者がいて、そのうち30人が翌月も再来店した場合:
リピート率 = 30 ÷ 100 × 100 = 30%
このように、数字で現状を把握することで、施策の効果検証や改善の方向性が見えてきます。
補足:期間設定(1ヶ月/3ヶ月など)や、新規・既存のカウント方法によってブレが出ることもあるため、自店で基準を明確にしておくことが大切です。
リピート率とリピーター率の違い
「リピート率」と「リピーター率」は似たような言葉に見えますが、意味も使い方も異なる別の指標です。混同しやすいため、正しく理解して使い分けることが大切です。
指標名 | 定義 | 主な用途 |
リピート率 | 新規来店者のうち、一定期間内に再来店した人の割合 | 再来店促進の施策評価 |
リピーター率 | 全来店者のうち、リピーター(複数回来店者)の割合 | 店舗のファン層の把握・維持 |
たとえば…
- リピート率が高い → 新規客が「また来たい」と感じた証拠
- リピーター率が高い → 常連が多く、安定した集客力がある状態
どちらも重要な指標ですが、「今どんな課題を改善したいか」によって注目すべき指標は変わります。
新規をリピーターにしたいなら「リピート率」、常連との関係強化を図るなら「リピーター率」をチェックしましょう。

飲食店の平均的なリピート率

飲食店のリピート率は、業態や立地、客層によっても差がありますが、全体的な平均値として参考になるデータもあります。
株式会社リクルートの調査(【飲食店リピート実態調査】リリース2019_Ver1002-1.pdf)によると、
外食におけるリピート利用の平均割合は約77.3%とされています。
つまり、外食の7〜8割は「一度行ったことのあるお店を再訪する」傾向があるということです。
業態別リピート率(目安)
業態 | 平均リピート率(目安) |
居酒屋系 | 約70〜80% |
カフェ | 約60〜70% |
ラーメン店 | 約50〜65% |
高級レストラン | 約40〜50% |
また、年齢や性別によっても傾向は異なり、40代以上や女性の方がリピート率が高いというデータもあります。これは「安心感」「習慣化」「コスパ重視」などの価値観が影響していると考えられます。
リピーター育成の鍵は“継続的な接点づくり 〜toypoの活用〜
/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
リピート率が重要であることはデータからも明らかですが、その割合を少しでも上げるためには、来店後もお客様との接点を持ち続けることが欠かせません。
ここで役立つのが、飲食店向けの販促支援ツール「toypo」です。
toypoでできること(一例)
- 来店履歴に応じたメッセージ配信(例:3回目来店で限定クーポン送信)
- 再来店を促すタイミングで自動フォロー(例:3週間来店がない人に再来店案内)
- 誕生日・記念日メッセージなどの配信
- デジタルスタンプカード・クーポンの発行・管理
- クーポン付き販促ページを無料で作成・共有(SNS・LINE・QRチラシなど)
デジタルで一人ひとりに合わせた接点を継続的に作ることで、リピート率はさらに向上させることができます。平均リピート率に満足せず、「もう一度来てほしいお客様」にきちんと届く仕組みを整えてみませんか?
/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
リピーターが多い飲食店の特徴
No. | 項目 | 特徴 |
1 | 料理・メニューに独自性がある | ここでしか食べられないと思わせる料理が再来店の動機になる |
2 | 接客が丁寧で親しみやすい | 笑顔や気配りで心地よい印象を与え、記憶に残る接客がリピートを促す |
3 | 店内が清潔で居心地が良い | 清潔感のある空間と居心地の良さがまた来たい気持ちを生む |
4 | 通いやすい価格帯 | 納得できる価格感がリピートを後押しし、通いやすさにつながる |
5 | 利便性がある立地・動線 | 駅近や駐車場の有無、スムーズな導線が通いやすさを支える |
6 | 定期的にクーポンや割引実施をしている | お得なきっかけをつくることで再来店を促進できる |
7 | 料理・メニューの質と独自性 | 味・見た目・ストーリー性のある料理が記憶に残りやすく再訪につながる |
8 | 価格の安さ・コストパフォーマンス | 価格に対する満足感(コスパの良さ)が日常的な利用を生む |
9 | 店内の清潔さと快適さ | 清掃・照明・BGMなど全体的な快適さが“また来たい”という印象を残す |
10 | 客層や雰囲気の魅力 | 落ち着ける客層や自然な接客など空気感そのものが再訪意欲を高める |
11 | 立地やアクセスの利便性 | 生活動線上の立地や通いやすさがリピーターづくりに貢献する |
リピート率が高い飲食店には、共通する強みや工夫があります。単に「味が良い」だけではなく「また行きたい」と思わせる総合的な体験を提供しているのが特徴です。
以下は、リピーターに愛されるお店に多く見られるポイントです:
1. 料理・メニューに独自性がある
味はもちろん、「ここでしか食べられない」「また食べたい」と思わせるオリジナル性がある料理は再来店の大きな理由になります。
2. 接客が丁寧で親しみやすい
スタッフの笑顔や気配りは、心地よい印象を残し、来店体験の満足度を高めます。「覚えてくれていた」が来店動機になることも。
3. 店内が清潔で居心地が良い
清潔感のある空間、適度なBGM、落ち着いた照明など、居心地の良さはまた来たい気持ちにつながります。
4. 通いやすい価格帯
価格設定が良心的で、コスパが高ければ自然とリピーターが増えます。安すぎず高すぎず、「納得できる価格感」が大切。
5. 利便性がある立地・動線
駅から近い、駐車場がある、待ち時間が短いなど、通いやすさもリピートされる要因です。
高リピート率の店舗は、「特別な体験」ではなく、「安心・快適・信頼」の積み重ねでリピーターを育てています。
リピーターが多い飲食店には、お客様が「また来たい」と思う理由が明確に存在しています。味・価格・空間・雰囲気といった基本的な要素がしっかり整っており、総合的に“満足できる体験”が提供されていることが共通点です。
6.定期的にクーポンや割引実施をしている
リピーターを増やすために効果的なのが、「お得なきっかけを定期的につくること」。特に、来店を迷っているお客様の背中を押す施策として、クーポンの配布や割引キャンペーンはとても有効です。
- 「〇日まで限定ドリンク1杯無料」
- 「次回来店時に使える100円OFFクーポン」
- 「雨の日割」や「曜日限定サービス」
こうした“ちょっと得する仕掛け”があることで、「また行こうかな」と思わせる動機づけになります。
▶ 紙クーポンより手軽な「デジタルクーポン」の活用もおすすめ
最近では、LINE公式アカウントやWebページから配布できるデジタルクーポンの活用が広がっています。紙と違って配布・管理が簡単で、再来店率アップに直結する便利な手段です。
デジタルチケット導入ならtoypo
/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
toypoは、飲食店向けに設計された無料の販促ページ作成ツールで、キャンペーン情報やクーポンを掲載したページを、誰でもかんたんに作れます。
toypoでできること(一部)
- クーポン情報を掲載したページが無料で作れる
- ページのURLやQRコードを発行でき、チラシやSNSとも連携可能
- LINE登録ページやGoogleマップ情報への導線もワンページで完結
- 特別な知識や設定なしでも数分で公開可能
たとえば、「LINE登録で使える限定クーポン」をtoypoで作成すれば、チラシにQRコードを貼るだけで簡単にキャンペーンが始められます。 新規の来店動機づくりはもちろん、リピーター育成にもピッタリです。

7.料理・メニューの質と独自性
リピーターが多いお店には、必ずと言っていいほど「この店ならでは」の料理やメニューがあります。味の良さはもちろんのこと、食材へのこだわりや調理法、盛り付け、ネーミングに至るまで、お客様の記憶に残る工夫がされているのが特徴です。
特に、「ここでしか食べられない」「またあの味が恋しくなって来た」と思わせるようなメニューは、再来店の大きな動機になります。見た目のインパクトや、SNSに投稿したくなる「映え」要素も今の時代は重要です。
一方で、奇をてらいすぎず日常の中でちょうど良い感動を提供できる料理こそが、長く愛されるお店の武器になります。味・見た目・ストーリー性の3点が揃ったメニューは、自然とファンを生み出していきます。
8.価格の安さ・コストパフォーマンス
リピーターを生む上で、価格の納得感は非常に重要な要素です。単に安いということではなく、料理の質やボリューム、接客、雰囲気などを含めて「この価格でこの内容なら満足できる」と思ってもらえるかどうかがポイントになります。
実際、多くのリピーターが評価するのは「コスパの良さ」です。「1,000円でこれだけ満足できるなら、また来よう」といった気持ちは、日常的な外食利用につながります。
また、価格設定が明確で安心感があることも大切です。メニューを見た瞬間に自分の予算に合っていると感じられるか、追加料金やサービス内容に不明点がないかなど、ちょっとした点がリピートに影響します。
コストを抑えながらも、お客様の期待値を上回る体験を提供できるお店は、結果として「通いたくなるお店」になります。
9.店内の清潔さと快適さ
どれだけ料理が美味しくても、店内が汚れていたり落ち着かない空間だと、お客様の満足度は一気に下がってしまいます。清潔で居心地の良い空間は、リピーターにとってまた来たいと思える安心材料であり、店舗の信頼にも直結します。
特に以下のポイントは、常連づくりにおいて非常に重要です。
チェックしたい清潔・快適ポイント:
- テーブル・イス・床などの拭き残しやベタつきがないか
- トイレや洗面所が常に清潔に保たれているか
- エアコンや照明のほこり・におい・明るさに配慮されているか
- 適度なBGMの音量や選曲が空間に合っているか
- お客様同士の距離や動線が窮屈でないか
清潔感は、見た目だけでなく「気遣いが行き届いているかどうか」の象徴でもあります。また、居心地の良さは、食事以外の体験全体の印象を左右するため、「また来よう」と感じてもらえる要素として非常に強力です。
10.客層や雰囲気の魅力
「また行きたい」と感じてもらえる飲食店には、そのお店ならではの空気感=雰囲気の魅力があります。その雰囲気は、料理や内装だけでなく、「どんなお客さんが来ているか」「スタッフの対応がどうか」といった「人の空気」からも生まれます。リピーターがつきやすいお店には、以下のような共通点が見られます。
リピートを後押しする雰囲気づくりの要素:
- 周囲のお客さんの層が自分に近くて安心できる(例:落ち着いた大人が多い、一人客が多い など)
- スタッフの声かけや表情が自然で気持ちいい
- 店内の会話の音量や距離感が居心地よく保たれている
- 過剰にかまわれすぎず、適度な距離感の接客がされている
- 店の雰囲気が自分の価値観や気分にフィットしている
雰囲気は数値化できない分、「なんとなく好き」「落ち着く」といった感覚で選ばれます。そのなんとなくを作るのが、空間×客層×接客のバランスです。「自分が過ごしたい空気」を提供できているか?を、ぜひお客様目線で見直してみましょう。
11.立地やアクセスの利便性
どれだけ料理や雰囲気が良くても、「行くのが不便」と感じさせてしまうお店には、リピーターはつきにくくなります。逆に言えば、通いやすさそのものがリピート理由になることも珍しくありません。リピーターが通いやすいと感じるポイントには、次のような要素があります。
アクセス面でチェックすべきポイント:
- 駅から徒歩○分以内、または大通り沿いなどわかりやすい立地
- 車利用の多いエリアでは駐車場の有無・台数が重要
- 雨の日でも入りやすいように屋根や導線が整備されている
- 通勤・通学・買い物など生活動線上にある(寄りやすい)
- 看板や店頭の装飾が目に留まりやすく、存在感がある
また、アクセスに特別な強みがなくても、「行く理由」をつくることは可能です。たとえば「この店に来るのが週末のごほうび」「あの席で一人になれる」など、心理的な利便性もリピートには大きく関わってきます。
リピーターを増やすと飲食店が得られるメリット

リピーターが増えることは、単に来店回数が増えるだけではなく、店舗経営の安定性や将来性にも大きく貢献します。一度来店したお客様が「常連さん」になることで、さまざまなプラスの効果が得られます。
1.外的要因に影響されにくくなる
不景気・天候・競合出店など外部環境の変化にも、リピーターが多いお店は強くなります。「今日はあの店に行こう」と思ってもらえる関係性があれば、一時的な波に左右されづらくなりす。
2.集客コストを削減できる
新規客の獲得にはチラシ、広告、SNS運用などコストや時間がかかりますが、リピーターは販促しなくても自然に来てくれるお客様です。結果として、広告費・労力を最小限に抑えながら売上を維持・向上できます。
3.良い口コミの拡散が期待できる
満足したリピーターは、友人に紹介したり、SNSに投稿したりと、自発的に無料で宣伝してくれる存在になります。特に常連になればなるほど、「応援したい気持ち」で口コミしてくれる確率も高くなります。
リピーターが増えない飲食店の問題

「一度は来てくれたのに、二度目がない」そんなお悩みを抱える飲食店は少なくありません。リピーターがつかない原因は、大きくお客様側の理由と店舗側の問題に分けられます。どちらも理解し、適切に対応することが大切です。
顧客側の理由(例:忘れている、引っ越し)
お客様のライフスタイルや状況が変わることで、自然と来店頻度が下がってしまうこともあります。
- 忙しくなって外食頻度が減った
- 引っ越しや転職でエリア外になった
- 単純に「忘れてしまった」
- 飽きやすい性格、他店開拓志向が強い
このようなケースでも、「思い出させる仕組み」や「再訪のきっかけづくり」でカバーできる可能性があります。
店舗側の課題(例:接客、味の低下)
お客様が「また来たい」と思えない理由が、店舗側にある場合も少なくありません。
- 初回来店の印象が薄く、強みが伝わっていない
- 接客がそっけなかった、あるいは過剰だった
- 料理のクオリティが不安定だった
- 店内が落ち着かない・清潔感に欠けていた
- 来店後に何のフォローアップ(LINE・クーポン等)もなかった
「リピーターが増えない=お客様の記憶に残っていない」という視点を持つことが、改善への第一歩です。
リピーターを増やすための具体的な施策

「また来たい」と思わせるには、ちょっとした工夫の積み重ねが何より大切です。
以下に、飲食店で取り入れやすいリピーター施策を7つご紹介します。
1.割引クーポンの配布
初回来店時に「次回使えるクーポン」を渡すことで、再来店のタイミングを後押しできます。
有効期限を設定することで、「近いうちに行こう」と思わせることも可能です。
2.ポイントカードの導入
「5回来店で1品無料」「10ポイントで割引」などの仕組みは、来店を習慣化させるのに効果的です。カードは紙でもデジタルでもOK。来店動機を明確にできます。
3.メールマガジンやDMの送付
来店後もつながり続ける手段として、定期的な情報配信は有効です。
季節のメニューやイベント、誕生日特典などの情報を届けることで、お客様との関係性が継続します。
4.定期的なメニューの見直し
新しい味の発見や季節感を取り入れることで、飽きられずに何度も来てもらえる理由が生まれます。
「前回来たときと違う料理が楽しめる」と思われるような工夫がポイント。
5.従業員の接客技術の向上
言葉遣いや気配り、表情など、接客の質はリピート率に直結します。
常連客の顔を覚える、好みを記憶しておくなど、小さな気遣いが効果的。
6.SNSの活用と情報発信
InstagramやLINEを使って、お客様と常につながりを保つ仕組みを作りましょう。
クーポン配信やメニューの裏側紹介など、見るだけでも楽しいアカウントが理想です。
7.オペレーションの改善
料理提供のスピードやレジでの対応、注文の通りやすさなど、お客様の体験全体のスムーズさがリピートに影響します。
忙しい時間帯ほど「無駄なく、丁寧に」が大切です。
まとめ:地道な販促とデジタル活用で安定経営を目指そう

飲食店経営において、リピーターは売上を支える最も安定した存在です。もちろん、新規集客に力を入れることも大切ですが、「また来たい」と思ってくれるお客様を育てていくことこそが、長く愛されるお店づくりには欠かせません。
その中でも特におすすめなのが、無料で始められる「toypo(トイポ)」のようなツールの活用です。 クーポン配布や再来店を促すページをかんたんに作成できるtoypoを使えば、デジタル販促が初めての方でもすぐに第一歩を踏み出せます。
チラシ・SNS・POPといったアナログ施策ももちろん効果的ですが、これからの時代は「デジタル販促」をいかに取り入れるかが、リピート率アップに大きく影響するポイントになっています。

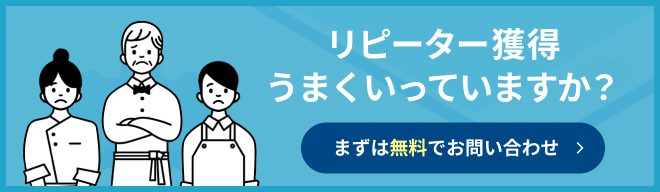


.jpg&w=1920&q=75)































.jpeg&w=1920&q=75)














.webp&w=1920&q=75)
.webp&w=1920&q=75)

