顧客満足度アンケートの作成方法とは?目的や活用するポイントを解説!
商品やサービスの質を高めるために、顧客満足度をアンケートで調査するのは欠かせません。どのように作成すれば良いかわからず悩んでいる方もいるでしょう。本記事では、顧客満足度アンケートの作成方法や実施する目的を解説します。
目次
- 顧客満足度調査を行う目的
- リピーターを獲得する
- 競合他社と比較する
- 商品やサービスの改善に繋げる
- 顧客満足度調査アンケートを実施するなら「toypo」
- 顧客満足度の指標
- 評定法による評価
- NPS®(ネット・プロモーター・スコア)
- CES
- ACSI
- 顧客満足度アンケートの作成方法
- 目的を明確にする
- 調査対象を決める
- 調査実施時期を決める
- 調査の実施方法を決める
- 設問を設計する
- アンケートを回収する
- 顧客満足アンケート結果を活用するポイント
- 定期的に調査を実施する
- フィードバックを行う
- 調査結果を分析する
顧客満足度調査を行う目的

顧客満足度調査を実施する目的は、顧客の声を正確に把握し、ビジネスの改善や競争力の強化につなげることにあります。より詳しく顧客満足度調査を行う目的を解説します。
リピーターを獲得する
顧客満足度調査の最も重要な目的の一つは、リピーターの獲得につなげることです。顧客が再度訪れるかどうかは、満足度に大きく左右されます。
調査を通じて顧客が満足している点や不満を感じている点を明確にすれば、リピート率を高めるための具体的な改善策を講じることが可能になります。
例えば、飲食店であれば、料理の味や提供スピード、スタッフの対応に対する顧客の意見を収集し、ポジティブな要素をさらに強化し、ネガティブな点を改善することで、より多くの顧客が「また来たい」と感じるような店舗運営を目指せるでしょう。調査結果はリピーター獲得における重要なデータとして活用されます。
競合他社と比較する
顧客満足度調査は、自店舗のサービスや商品が競合他社と比較してどの位置にあるのかを把握する手段としても有効です。調査結果を基に、自社の強みや弱みを明確にし、競合と差別化を図るための戦略を立てることができます。
調査の中で「他店と比べて価格が高い」「サービスの質が優れている」などのフィードバックが得られた場合、価格競争に巻き込まれずに価値を提供するための付加サービスを強化する、といった方向性を定めることが可能です。競争の激しい業界で生き残るためには、比較データを活用した独自の魅力づくりが重要です。
商品やサービスの改善に繋げる
調査の結果から得られる顧客の声は、商品やサービスの改善に直接結びつきます。新メニューの開発時や既存商品のリニューアル時に、顧客が求める味や価格帯、デザインのヒントが得られます。また、接客や店舗の雰囲気、注文プロセスなど、サービス全体の品質向上にも役立つでしょう。
具体例として、「接客が良かった」という評価が多ければ、その接客スタイルを標準化することで店舗全体のクオリティを上げることができます。一方で「待ち時間が長い」という不満が見つかった場合、スタッフの増員やキッチンの効率化を検討しなければいけません。調査データは改善を行う上での具体的な指針となります。
顧客満足度調査アンケートを実施するなら「toypo」

toypoは飲食店のリピーター獲得に繋げられるサービスであり、スタッフに代わって販促活動を行ってくれます。そのため、リピーター獲得のためにリソースを割く必要がありません。
クオリティの高い分析によって、顧客に合わせたアプローチが実施可能になるのもtoypoの魅力です。飲食店のリピーター獲得に悩んでいる方は、ぜひtoypoを活用してください。
/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
toypoの顧客満足アンケート機能について詳しくはこちら↓
https://toypo.me/features/survey-for-customer-satisfaction
toypoの顧客満足アンケート機能を活用した事例はこちら↓
顧客満足度の指標

顧客満足度には、主に4つの評価指標があります。ここでは、それぞれの評価指標について詳しく解説します。
評定法による評価
評定法は、顧客に対して「満足度」を数値や段階で評価してもらう最も一般的な手法です。例えば、1(非常に不満)から5(非常に満足)までの5段階評価や、1〜10のスコアを用いることが一般的です。
評定法はシンプルで、顧客にとっても回答が容易であるため、多くの飲食店でアンケートやオンライン調査に採用されています。
評定法のメリットは、結果が直感的に理解しやすい点にあります。平均スコアや分布を分析することで、全体の満足度や改善が必要な部分を簡単に特定可能です。
ただし、顧客が選択肢をどう解釈するかは主観的であるため、同じスコアでも異なる背景がある可能性がある点に注意が必要です。
NPS®(ネット・プロモーター・スコア)
NPS®は、顧客がその飲食店を他人に薦める可能性を評価する指標です。「このお店を家族や友人に薦めたいと思いますか?」という質問に対し、0(まったく薦めたくない)から10(非常に薦めたい)までのスコアを回答してもらいます。
その後、スコアに応じて顧客を「推奨者(9〜10)」「中立者(7〜8)」「批判者(0〜6)」に分類し、スコアを算出します。
NPS®は顧客ロイヤルティの指標として広く活用され、単なる満足度にとどまらず、ブランドに対する顧客の信頼や愛着を示します。この指標を活用すれば、リピーター獲得や新規顧客の紹介を促進する戦略を立てることが可能です。
CES
CESは、顧客が飲食店を利用する際にどれだけ「努力」が必要だったかを測定する指標です。例えば、「注文がスムーズだったか」や「不快に感じる点はなかったか」など評価する際に用いられます。「非常に簡単だった」から「非常に難しかった」までのスケールで回答を求めることが一般的です。
CESは顧客体験(CX)の改善に役立つ指標です。特に、注文時の利便性やスタッフの対応、トラブル解決の迅速さなど、顧客の負担を軽減する施策を検討する際に有効です。
低いスコアは、プロセスのどこかに無駄やストレスがあることを示しているため、改善すべき具体的なポイントを特定しやすくなるのが特徴です。
ACSI
ACSIは、顧客の期待、実際の体験、そしてその体験の価値について総合的に評価する指標です。主に米国で活用されていますが、基準が広範であるため、さまざまな業界や国での比較に役立つのが特徴です。
ACSIは複数の質問項目を用いて満足度を測定し、スコアを算出します。ACSIの強みは、顧客満足度が売上や利益にどのように影響するかを把握できる点です。
そのため、長期的な顧客関係の構築や市場シェアの拡大を目指す場合に重要な指標となります。ただし、質問項目が多いため、調査を実施する際には顧客の負担を考慮する必要があります。
顧客満足度アンケートの作成方法

顧客満足度アンケートは6つのステップで作成します。それぞれのステップについて詳しく解説します。
目的を明確にする
最初に、アンケートを行う目的を明確にすることが重要です。例えば、「新商品の評価を知りたい」「接客に関する意見を収集したい」「リピーターが少ない原因を探りたい」など、具体的な目標を設定します。
目的をはっきりさせれば、適切な設問を作成しやすくなり、回収したデータを有効活用しやすくなるでしょう。曖昧な目的では、分析の焦点がぼやけてしまうため、成果が得られにくくなる点に注意が必要です。
調査対象を決める
次に、アンケートを実施する対象を明確にします。すべての顧客を対象にするのか、それとも特定の条件を満たす顧客(例:新規顧客や常連客)を対象にするのかを決定します。
飲食店では平日利用者と週末利用者の満足度を比較する場合、それぞれを別々に調査することが効果的です。対象を絞り込むことで、より詳細で有益なデータを得ることができます。
調査実施時期を決める
アンケートの実施時期も成功の鍵を握ります。顧客の体験が記憶に新しいうちに実施するのが理想的です。
例えば、飲食店の場合、会計時や来店直後にアンケートを依頼することで、回答の正確性を高めることができます。
また、繁忙期やキャンペーン期間中の調査は、通常時とは異なるデータが得られるため、それぞれの時期に合わせて実施を計画すると良いでしょう。
調査の実施方法を決める
調査をどのように実施するかも重要な要素です。紙のアンケート用紙を使用する、オンラインフォームを活用する、またはQRコードで簡単にアクセスできる形式にするなど、顧客にとって回答がしやすい方法を選びます。
また、対面でのインタビュー形式を採用する場合、より具体的な意見を聞き出せる利点があります。一方で、オンライン形式では集計が簡単で、より多くの回答を短期間で得ることが可能です。
設問を設計する
設問の設計はアンケートの質を左右する重要なステップです。目的に合わせて必要な情報を引き出せる質問を用意し、回答が簡単な形式にします。
例として、「料理の味に満足しましたか?」という具体的な質問や、「満足度を1から5で評価してください」といった評定法を活用します。
選択肢のある設問に加えて、自由記述の欄を設けることで、顧客の具体的な意見を収集することも可能です。しかし、設問数は長くなりすぎないよう注意し、回答の負担を軽減しましょう
アンケートを回収する
最後に、アンケートを回収する仕組みを整えます。顧客がスムーズに提出できる環境を作り、可能であれば回答のお礼として特典を提供すると、回収率が向上します。
次回利用時の割引クーポンを進呈するなど、顧客にメリットを感じてもらう方法が効果的です。また、オンライン形式では回収と同時にデータがデジタル化されるため、後の分析作業が簡単になります。
顧客満足アンケート結果を活用するポイント

顧客満足度アンケート結果を活用するポイントは以下の3つです。それぞれ詳しく解説します。
定期的に調査を実施する
顧客満足度は一時的なものではなく、時間の経過や外部要因によって変動する可能性があります。そのため、アンケート調査は一度きりで終わらせるのではなく、定期的に実施することが重要です。
定期的に実施することで、顧客の満足度の変化やトレンドを把握しやすくなり、長期的な改善施策を立てるためのデータを蓄積できます。
例えば、飲食店では季節限定メニューや新サービスを導入する際にタイミングを合わせて調査を行うと、これらの施策が顧客に与えた影響を把握できます。また、継続的な調査により、顧客がどのような要素を最も評価し、何に不満を感じているのかを定期的に確認できるため、現状を適切に評価しやすくなるでしょう。
フィードバックを行う
顧客からの意見を受け取ったら、その内容に対して適切なフィードバックを行うことも重要です。顧客は、自分の意見が店舗運営に反映されていると感じることで、店舗への信頼やロイヤルティが向上します。
例えば、アンケートで寄せられた要望に応じてメニューを改善したり、新しいサービスを導入した場合、その取り組みを顧客に知らせることで「意見が反映されている」という実感を持ってもらえます
フィードバックは、店内ポスターや公式SNS、メールマガジンなどを活用して広く共有することが効果的です。また、「お客様の声をもとにこのメニューが誕生しました」といった具体的な事例を紹介することで、顧客との対話を活発化させることができます。
調査結果を分析する
アンケート結果をただ集めるだけでなく、詳細に分析することが必要です。分析を行うことで、顧客満足度を左右する要因や、具体的な改善が必要な課題を特定できます。例えば、調査結果を属性ごと(年代、性別、利用頻度など)に分類して分析することで、特定の顧客層がどのようなニーズを持っているのか把握できます。
さらに、時系列でデータを比較し、過去と現在の満足度を比較することで、施策の成果を確認することも可能です。また、定量的なデータだけでなく、自由記述の意見をテキスト分析することで、定性的な洞察を得ることも効果的です。このような分析を基にした改善施策を実行することで、アンケート結果をより実践的な形で活用できます。
顧客満足度アンケートは商品やサービスの質の向上に欠かせない

顧客満足度アンケートは、商品やサービスの質を高めて、売り上げを向上させるために欠かせません。定期的に実施し、現場に反映していきましょう。ぜひ、本記事を参考にして、顧客満足度アンケートを実施してみてください。

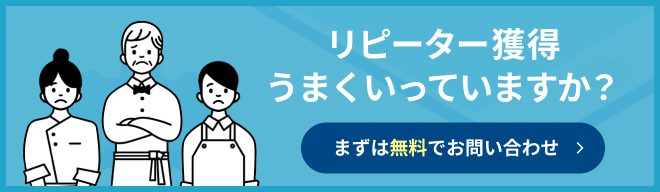


.jpg&w=1920&q=75)































.jpeg&w=1920&q=75)














.webp&w=1920&q=75)
.webp&w=1920&q=75)

