飲食店の経営は難しい?成功させるためのポイントを徹底解説!
飲食店の経営は難しいというイメージがある方は多いのではないでしょうか。実際に経営がうまくいかずに倒産してしまう飲食店は少なくありません。しかし、正しい方法で経営を行えば、飲食店を成功させることは十分に可能です。本記事では、飲食店の経営が難しい理由について紹介します。成功させるポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 飲食店の経営が難しい理由
- 飲食店の経営を成功させるコツ
- 飲食店の経営が傾いた場合の対策
- 飲食店の経営を安定させるなら「toypo」を活用しよう!
- 飲食店の経営に関するよくある質問
飲食店の経営が難しい理由

飲食業は廃業率が高い業界として知られています。その理由としては、飲食業特有のリスクや構造的な課題が挙げられます。ここでは、飲食店経営が難しいとされる主な理由について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
- 食材の価格が変動するリスクがある
- 競合が多く顧客の獲得が困難
- 利益率が低く固定費の負担が大きい
- 人手を確保するのが難しく人件費も高い
- 口コミやSNSでの悪評リスクがある
食材の価格が変動するリスクがある
飲食店経営において避けて通れないのが、食材価格の変動リスクです。野菜や魚、肉類などは、天候や災害、輸入状況などさまざまな要因で価格が日々変動します。特に原価率の高いメニューを多く取り扱っている店舗では、わずかな価格上昇でも利益が圧迫されるケースがあります。
価格変動を読み切るのは困難なため、常に仕入れ先を見直したり、代替メニューを準備したりして柔軟に対応しなければいけません。
競合が多く顧客の獲得が困難
飲食業界は参入障壁が比較的低く、開業する店舗の数も多いため、競争が激しいです。同じエリアに類似業態の店舗が複数存在することも珍しくなく、価格競争やサービス競争が日常的に起こります。
特に都市部では、顧客が簡単に他店に流れてしまうため、継続的に集客できる魅力がなければ経営を続けられません。差別化のためのブランディングやマーケティングの重要度は高いといえるでしょう。
利益率が低く固定費の負担が大きい
飲食店の利益率は、数ある業種の中でも決して高い方ではありません。原材料費・人件費・家賃・光熱費・広告宣伝費など、日々の運営にかかるコストが多岐にわたり、売上が安定していなければすぐに赤字に転落してしまうこともあります。
また、席数や客単価によって売上の上限があるため、効率的な運営が欠かせません。売上が伸び悩む中で固定費が重くのしかかると、経営を継続できなくなる可能性があります。
人手を確保するのが難しく人件費も高い
近年の飲食業界では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。求人を出しても応募が集まらない、採用できてもすぐに辞めてしまうといったケースも多いです。
人手を確保するために待遇を良くすると、人件費がさらに膨らみ、利益を圧迫してしまいます。また、十分な人員が確保できないと、オペレーションにも支障が出て、サービス品質の低下を招く可能性もあるため注意が必要です。
口コミやSNSでの悪評リスクがある
現代の飲食店経営において無視できないのが、SNSや口コミサイトの存在です。良い評価が集まれば集客につながる一方で、たった一つの悪評が拡散されることで、店舗の信頼が大きく損なわれる可能性があります。
誤解や事実と異なる情報が投稿されることもあるため、SNS対策は飲食店の経営において欠かせないといえるでしょう。
飲食店の経営を成功させるコツ

飲食店経営は難しい点も多いですが、正しい戦略を立てて工夫をして経営を行えば、十分に成功することが可能です。ここでは、飲食店を安定して成長させるための具体的なコツを紹介します。
- 飲食店のコンセプトを明確にする
- 立地選びを慎重に行う
- 収支計画を詳細に考える
- 適切な原価管理と無駄の削減を徹底する
- SNSや口コミを活用する
- リピーターを増やす工夫を行う
- スタッフの教育を徹底する
- 業務を効率化するためにデジタルツールを導入する
飲食店のコンセプトを明確にする
店舗の成功において最も重要なのが「コンセプト」です。どのようなターゲット層に向けて、どんな価値を提供するのかが明確になっていなければ、顧客に店舗の魅力が伝わりにくくなります。逆にコンセプトが明確な店舗は、口コミでも認知されやすく、リピーターも獲得しやすいです。
立地選びを慎重に行う
飲食店の立地は、集客力に大きな影響を与えます。人通りの多さだけでなく、ターゲット層との相性や周辺の競合状況、駐車場の有無なども考慮する必要があります。
例えば、ファミリー層をターゲットにしている場合は、住宅街やショッピングセンター付近、ビジネス層向けならオフィス街に店舗を構えるのが理想的です。また、賃料とのバランスも考える必要があります。
収支計画を詳細に考える
飲食店を経営する上で、売上だけでなく支出も含めた詳細な収支計画は欠かせません。開業時の初期費用や運転資金、月々の家賃や人件費、仕入れコストなどを正確に把握し、損益分岐点を意識して経営を行う必要があります。
収支計画がしっかりしていないと、予期せぬ出費があった際に経営が傾く可能性が高くなるので注意しましょう。
適切な原価管理と無駄の削減を徹底する
利益を出すためには、仕入れのコストと販売価格のバランスを保つことが大切です。適切な原価率の設定やロスの少ない仕入れ・仕込み体制を整えることで、無駄を減らして利益率を高めることが可能になります。
また、在庫管理を怠ると廃棄ロスが増え、コストがかさむ原因になるため、定期的な棚卸しや在庫の最適化も重要です。
SNSや口コミを活用する
近年では、SNSや口コミサイトの影響力が大きくなっています。インスタグラムやX(旧Twitter)、Googleマップなどを活用して自店舗の情報を発信し、認知度を高めることが飲食店を成功させる上で重要です。
また、来店客からのレビューを積極的に集め、ポジティブな評価を広めていくことで、新規顧客の獲得にもつながります。キャンペーンや限定メニューなどもSNSを通じて宣伝すれば、販促効果を高めらるでしょう。
リピーターを増やす工夫を行う
飲食店の安定経営には、リピーターの存在が欠かせません。一度きりの来店ではなく、何度も通ってもらえるような工夫が必要です。
例えば、スタンプカードやポイント制度などの導入、季節限定メニューの提供、店員とのコミュニケーションの強化などが挙げられます。リピーターを増やすことで、集客コストを抑えながら安定した売上を維持することができます。
スタッフの教育を徹底する
サービスの質は店舗の印象を大きく左右します。どれだけ料理が美味しくても、接客が悪ければリピートにつながりません。
新人スタッフに対する接客マナーの教育や、クレーム対応の研修などを行うことで、店舗全体のサービスレベルを底上げできます。また、スタッフのモチベーションを維持するために、表彰制度や昇給制度を整えることも重要です。
業務を効率化するためにデジタルツールを導入する
近年では、業務効率化を図るためのさまざまなデジタルツールが登場しています。POSレジ、モバイルオーダー、在庫管理システム、シフト管理アプリなどを導入することで、手作業にかかっていた時間や人的ミスを減らし、スタッフの負担を軽減できます。
結果として人件費の最適化や顧客満足度の向上にも繋がるでしょう。

飲食店の経営が傾いた場合の対策

どれだけ準備をして飲食店を開業しても、想定外の出来事や時代の変化によって経営が思うようにいかなくなることもあります。しかし、早期に適切な対策を講じることで、経営の立て直しは可能です。ここでは、飲食店の経営が傾いた際に実施するべき具体的な対策を紹介します。
- 支出の見直しと固定費の削減を行う
- メニューの見直し・削減を行う
- 販促活動を強化する
- 営業時間や営業スタイルを見直す
- 専門家に相談して経営改善計画を立てる
支出の見直しと固定費の削減を行う
まず取り組むべきなのが、支出の見直しです。家賃、人件費、水道光熱費などの固定費は、売上が落ちた時に大きな負担となります。
例えば、人件費の調整のために営業時間の短縮やスタッフのシフト見直しを行ったり、契約している業者との仕入れ価格交渉を行ったりすることが効果的です。電力プランや通信環境の見直しによって月額コストを下げることも、経営の安定化に役立つでしょう。
メニューの見直し・削減を行う
多くの飲食店が売上回復のためにメニューを増やす傾向にありますが、むしろ逆効果になるケースもあります。具体的にはメニュー数が多いと仕入れや管理が複雑になり、食材ロスが発生しやすくなります。
コストパフォーマンスの悪いメニューは思い切って削除し、原価率が安定している人気メニューに絞り込むことで、利益率の向上が狙えるかもしれません。また、限定メニューや季節商品などを展開して、話題性を出すのもおすすめです。
販促活動を強化する
売上が落ち込んでいるときこそ、販促活動に力を入れる必要があります。既存顧客への再来店を促すためにLINE公式アカウントやSNSを活用したクーポン配布を行ったり、チラシやポスティングを通じて近隣住民に認知を広げたりすることが有効です。
また、食べログやGoogleマップなどのレビューサイトを活用して高評価を集め、飲食店への信頼を集めるのもおすすめです。
営業時間や営業スタイルを見直す
時代の変化や地域のニーズに合わせて営業スタイルを柔軟に変更することも効果的です。例えば、昼間のランチ営業を新たに始める、テイクアウトやデリバリーに対応する、間借り営業やキッチンカー展開などで収益の柱を増やすといった方法があります。
専門家に相談して経営改善計画を立てる
経営の立て直しに行き詰まってしまった場合は、一人で悩まずに外部の専門家に相談するのもおすすめです。中小企業診断士や経営コンサルタント、商工会議所などの専門機関は、無料または低価格で相談できる制度が整っています。
第三者の目で経営における課題を客観的に見直し、改善計画を立てましょう。
飲食店の経営を安定させるなら「toypo」を活用しよう!

飲食店の経営を成功させるうえで、日々の業務効率を高めることは重要です。飲食店の業務の効率化を目指すなら、飲食店向けの業務効率化ツール「toypo(トイポ)」を導入してみてください。
toypoは、飲食店に特化したデジタルマーケティング・顧客管理支援ツールです。来店客に対するメッセージ配信、クーポンの発行、予約管理などを一元的に行うことが可能です。また、ポイントカード機能やアンケート機能を活用することで、顧客の動向を把握し、再来店の促進につなげられる点も魅力の1つです。
手間のかかる販促業務を自動化できるため、現場スタッフの負担も軽減され、顧客満足度の向上にもつながります。管理画面は直感的で操作しやすく、ITに不慣れなスタッフでも短時間で使いこなせる設計となっており、中小規模の飲食店でも導入するハードルが低いのが特徴です。
ぜひtoypoを導入して、飲食店の業務効率化を図ってみてください。
飲食店の経営に関するよくある質問

飲食店の経営に関するよくある質問について回答します。これから飲食t飲食店の経営を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
- Q. 飲食店経営者の平均年収は?
- Q. 飲食店を開業するのに必要な資格は?
- Q. 飲食店の開業に必要な資金は?
- Q. 飲食店の利益率を高めるコツは?
- Q. 飲食店の人手不足を解消する方法は?
Q. 飲食店経営者の平均年収は?
1飲食店経営者の年収は店舗の規模や立地、業態によって大きく異なりますが、全国平均ではおおよそ300万円〜600万円程度が一般的とされています。繁盛している店舗や複数店舗を展開しているオーナーであれば、年収1,000万円を超えるケースもあります。
Q. 飲食店を開業するのに必要な資格は?
飲食店を開業するには、「食品衛生責任者」の資格取得が必要です。これは1日の講習を受講することで取得できます。また、店舗を営業するには保健所の営業許可も必須です。業態によっては「防火管理者」や「酒類販売業免許」など、追加で必要となる資格・許可もあるため、事前に確認しておきましょう。
Q. 飲食店の開業に必要な資金は?
飲食店の開業資金は、業態や規模により異なりますが、小規模な個人経営の飲食店であれば500万円〜1,000万円程度が目安となります。主な内訳は、店舗の物件取得費、内装・設備費、開業準備費、運転資金などです。
資金調達においては、日本政策金融公庫などの創業融資制度を活用するケースも多く見られます。
Q. 飲食店の利益率を高めるコツは?
飲食店の利益率を高めるには、原価率の管理と無駄な支出の削減が基本です。特に食材ロスを減らす工夫や、メニューの見直し(高粗利メニューの導入)を行うことが効果的です。
また、人件費や水道光熱費の最適化、POSレジなどによる業務効率化も利益率の向上に繋がります。
Q. 飲食店の人手不足を解消する方法は?
人手不足の解消には、働きやすい職場環境の整備と、業務の効率化が重要です。スタッフの定着率を高めるためには、シフトの柔軟性、評価制度の整備、研修体制の強化などが効果的です。
また、toypoのようなデジタルツールを活用して業務を簡素化することで、少人数でも効率よく店舗運営が可能になります。

飲食店は工夫して経営を行えば十分に成功できる!

飲食店は立地選びを慎重に行ったり、デジタルツールを導入したりして工夫して経営を行えば十分に成功可能です。飲食店を初めてみたいけれど成功するか不安という方は、ぜひ本記事で紹介した経営のコツを参考にしてみてください。便利なツールも数多くあるので、積極的に活用しましょう。

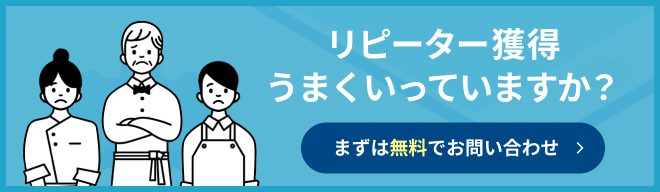


.jpg&w=1920&q=75)































.jpeg&w=1920&q=75)














.webp&w=1920&q=75)
.webp&w=1920&q=75)

